発明発掘とは?企業の知財部員が解説します!
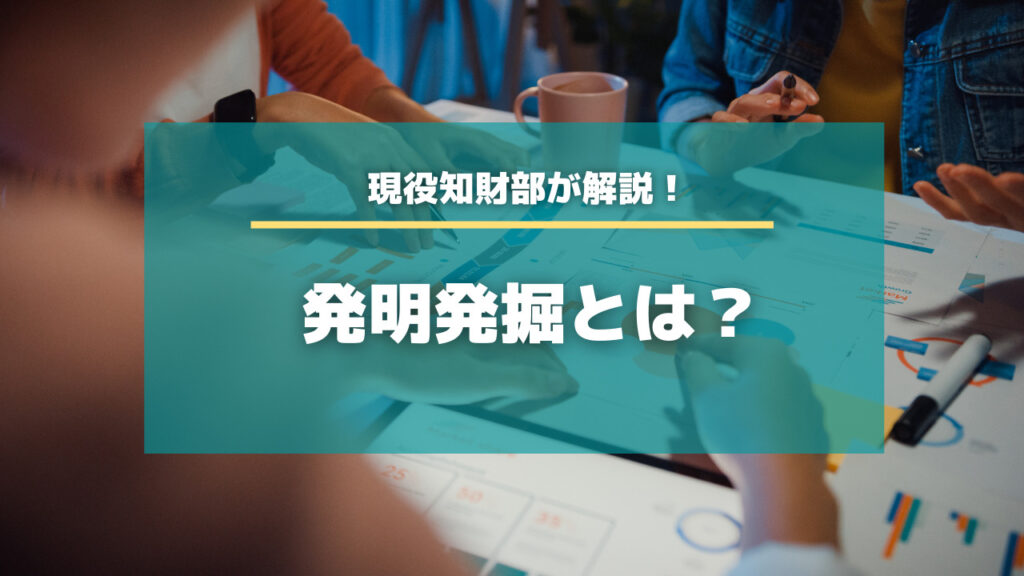
企業の知財部にお勤めの方で、
技術・研究・開発部門からなかなか発明提案が出てこない!
とお悩みの知財部の方もいらっしゃるのではないでしょうか?
発明提案が出てこなければ、出願もできませんし、権利を取得することもできません。更には、取得した権利を経営戦略に生かすこともできません。
新しい製品が開発されたり、改良された製品が開発されれば、きっとそこには発明が隠れています!
本記事では、知財部の主な業務の一つである発明発掘について解説していきます。知財部に配属されたばかりの人や、今後知財部への異動・転職を考える方は是非参考にしてみてください。
発明発掘とは?
開発者の持つ情報の中に埋もれてしまっている新しい技術的アイデアを引き出すことで形にし、新しい発明を生み出していくこと、これを発明発掘といいます。
技術研究・開発などの毎日の業務の中で生まれるアイデアは、開発者が気づかないうちに発明として完成しているかもしれません。
知財部は開発者からこのような発明を発掘していくことが重要です!
なぜ発明発掘は重要?
なぜ企業にとって発明発掘が重要なのか?
それは企業の知財部は、開発者が気づいていない発明を発掘していかなければ、自社技術を出願・権利化することはできないからです。
また発明発掘を行うことで、開発者が気がつかなった用途や手段を発見できることもあり、結果として権利範囲の広い特許(強い特許)を取ることができるかも知れません。
開発者は、日々の業務の中で様々な工夫をして技術開発に取り組んでいると思います。
日頃から、
「これは新しい技術だ!」
「この業務で発明をしたい!」
など考えて業務に取り組んでいる開発者であれば、知財部は発明発掘を行う必要性は低いかもしれません。
しかし、自ら発明提案をしてくれる開発者はおそらく多くはなく、開発者は日々の業務に追われて新しい技術を生み出していることに気づかない方がほとんどではないでしょうか。
また、発明意識の高い開発者であっても、自分では気づかない発明がまだ隠れているかもしれません。
知財部と開発者とで発明発掘会議を行なった時に、開発者から
「これが発明になるんですね?!」
「これは当たり前の技術だと思っていました!」
と言われるのはよくある話です。
新しく発明された技術が気づかれないまま埋もれてしまうのと、特許出願をして権利化するのとでは、企業の経営戦略に大きな差が出ることは間違いありません。
このようなことを防ぐために、知財部は開発者と定期的に打ち合わせを行い、発明を発掘していくことがとても重要です。
知財部はどのような点に気をつけて発明発掘するべきか?
開発者と発明発掘の会議を行う場合、「どのような発明をしましたか?」などと尋ねても、発明をしたという意識のない開発者にとってはどう答えてよいか分からないこともあるでしょう。
知財部は以下のようなことに気をつけて、発明者から発明を発掘しましょう!
開発時の課題を明確に
新しい製品を開発した場合、なぜそのような製品を開発したのか理由があるはずです。
例えば、
- 今までの製品には不具合があったためそれを解消する必要があった
- 今までの製品にはなかった機能をつけた方がより良い製品になると考えた
- 今までの製品は製造コストが高かった、製造工程が複雑だった
などがあると思います。
今までの製品の問題点、改良すべき点を明確にすれば、その点についての解決方法として、どのような技術を考えたのかがはっきり見えてくるはずです。
開発者が発明したと思っていない技術であったとしても、それが発明である可能性がありますのでそれを見落とさないように発掘しておきましょう。
発明のバリエーションを考える
一つの発明が発掘できたからと言って、それで終わってしまってはいけません。
一つの発明から複数のバリエーション(実施例)を考えることで、権利化されたときにより広い権利内容となります。
例えば部品を固定するために「ねじ」を用いたという発明があったとします。
この部品を固定する手段として「ねじ」だけではなく、他の手段でも可能であるのかを開発者に確認します。もし、他の手段、例えば「接着剤」や「シール」、「溶着」などでも実施可能であれば、それを実施例として特許明細書に記載します。
実施可能なバリエーションを多く特許明細書に記載し、権利範囲に含められれば、より強い権利になってきます。
発明の上位概念を考える
開発した製品の技術だけでは、権利化した場合に権利内容の狭い権利となってしまいます。
先ほどの、部品を固定するために「ねじ」を用いたという発明があった場合を考えます。
その固定が「接着剤」や「シール」、「溶着」でも可能であった場合、「部品をねじで固定する」という表現ではなく、「部品を固定手段で固定する」という上位概念化した表現の方が、権利内容が広くなります。
しかし、闇雲に上位概念化しても、開発した製品が「ねじ」以外の固定が不可能なものでしたら、上位概念で権利化しても審査段階で指摘される可能性があります。
今回の発明技術が、上位概念化して実施可能であるかどうかを、開発者に確認する必要があります。
不採用案があるか
製品開発にあたって、開発者は様々な工夫をし、課題を解決するために沢山の解決案を考えたと思います。
今回の製品に不採用だった技術であったとしても、不採用案も発掘しておく価値はあります。
不採用案は同じ課題に対する解決手段であり、今後の製品開発において採用される技術になるかもしれませんし、他社が考えついて特許出願する可能性もあります。
また、今回の発明が権利化された場合、他社が権利回避するために別の技術(=不採用案の技術)を考案して権利抵触を防ぐかもしれません。
不採用案だったとしても、その技術内容が出願する価値があるかもしれませんので、是非開発者に尋ねてみましょう。
まとめ
発明は開発者による日々の業務活動の中で、気づかないうちに生み出されていることも多いです。
しかし、多くの発明が気づかれず埋もれたままになっており、特許出願されずに製品化されることもあります。
出願前に製品が世の中に出てしまえば、その技術を出願できなくなってしまいます。
知財部はそのようなことにならない為にも、開発者と定期的に打ち合わせを行い、業務内容のヒアリングや発明発掘を行い、早めに特許出願に結びつけることが重要です。
知的財産を企業戦略に生かすため、日々の業務に埋もれた発明を発掘し、出願、そして権利化を目指していきましょう!
知財部の業務に関する記事
- 知的財産に関する業務とは?知財部の仕事内容
- 知財部で働くために英語は必要?知財部経験者が解説します!
- 発明発掘とは?企業の知財部員が解説します!
- 知財管理ってどんな仕事?知財部が解説します。
- 企業の知財部員に求められるスキルとは?レベル別に解説します!
- 知財戦略とは?企業知財部が成功事例もあわせて解説!
- 特許マップ(パテントマップ)の作り方!知財部員がやさしく解説!
- 超簡単!特許調査のキホンを企業知財部員が解説
- 知財部員が受ける研修とは?
- 現役知財部が解説!知財部におすすめのセミナー
知財専門の求人サイト「知財HR」
知財業界はいわゆるニッチ業界。そこで転職時に重要になってくるのが「どれだけリアルな情報を集められるか」です。特に知財部の仕事は明細書を内製するか/外注するかなど、企業ごとに扱う業務がまったく違うので、いっそうの注意が必要です。
知財HRでは、そんな転職前の不安・お悩みにこたえるべく、求人票にインタビューを掲載中!(※求人によります)
事業内容からはじまり、より具体的な仕事内容、職場の雰囲気、求人募集の背景など…。たくさんのリアルな情報を知ったうえで求人へ応募することができます!求人検索は下のボタンから↓↓↓
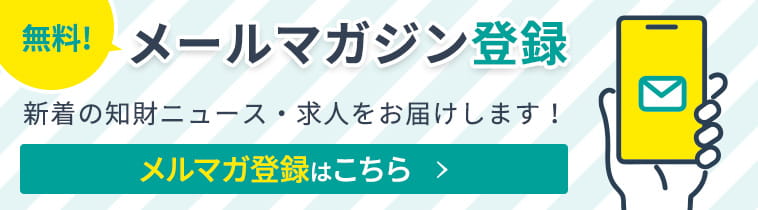

家電メーカー、遊技機メーカーの知財部として20年以上勤務。
出願、調査から無効審判、特許訴訟、特許管理業務まで色々な知財業務を担当したワーキングママです♪
趣味はピアノ。知財歴より長い30年以上!人気のあるアニメ曲を弾いて、子供たちに好かれようとしています笑

