産学連携について解説します
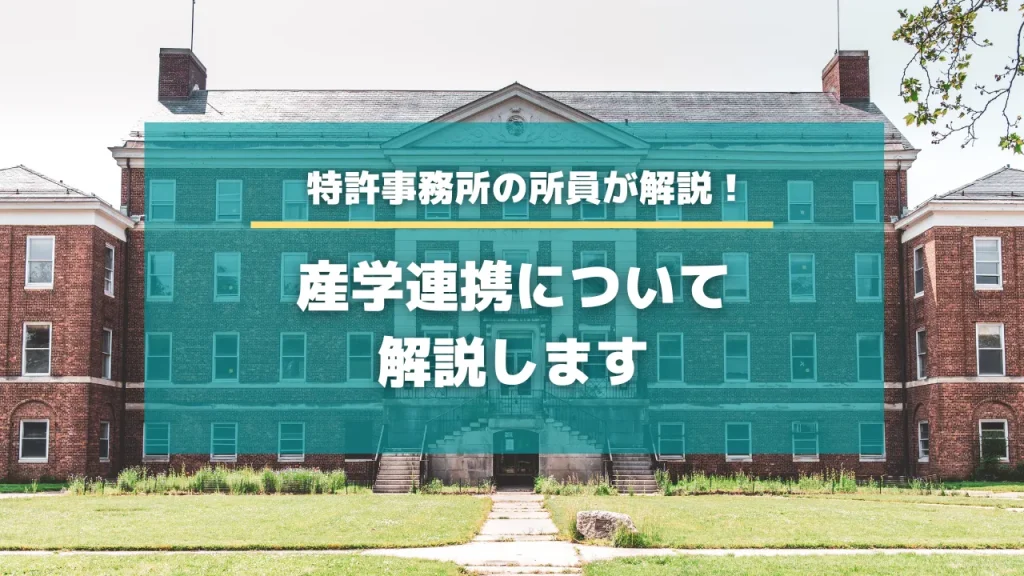
産学連携(産官学連携)は、社会的・経済的ニーズに対応した研究開発の推進と、知的資産を生み出す基礎研究の積極的な振興を目的として、「産学官連携の強化」を掲げ、導入された制度です。
近年では、人工知能や量子コンピュータ、ビッグデータを用いた技術革新(第四次産業革命)が急速に進み、技術がより複雑化・高度化しています。
この技術革新が急速に進んでいる状況下における産学連携(産官学連携)はどうなっているのか?今回はその現状について、解説します。
産学連携とは(産官学連携とは)
産学連携とは、大学などの研究・教育機関と、民間企業が連携することで、教育・研究・技術開発・人材育成などを進める取り組みです。
「産」は「産業界(民間企業)」、「学」は「大学など」を指します。また、この産学連携に政府や地方公共団体を意味する「官」を加えて、「産官学連携」または「産学官連携」と呼ぶこともありますが、「産官学連携」と「産学官連携」については、特に違いはありません。
産学連携と産学官連携の違いはなにか
産学連携と産官学連携の違いとしては、先ほど述べた対象者の他、提携目的として以下の相違点が挙げられます。
- 産学連携:「技術開発」「研究成果の実用化」「人材育成」等
- 産官学連携:「技術開発」「研究成果の実用化」「人材育成」の他、「社会課題の解決」「地域振興」「政策形成」等
また産官学連携は「官」と提携するため、産学連携と比べてプロジェクトが大型化する傾向にあります。
産学連携の狙い
産学連携の狙い(意義)については、文部科学省から公表されている資料があります。
文部科学省が産学連携を推進する狙いとしては、まず、人工知能等の技術の進展を背景としたグローバリゼーション(世界的規模での競争市場の出現)が浸透することにより、「選択と集中」をベースとし、社会の変化に迅速に対応する企業が求められているという状況があります。
また大学としては、産業界のニーズにも配慮しつつ独創性のある実践的な人材を輩出することがより強く求められていることや、社会的問題の解決などを主眼とした研究様式が認識されてきている、という状況があります。
さらには諸外国で、科学技術への効率的投資、研究成果の活用やこれに基づく起業支援等を通じて、イノベーションシステムの構築を試みる動きが広まっています。
このような状況を鑑み、我が国では「産」、「学」、「官」がそれぞれの使命・役割の違いを理解し尊重しつつ、双方の活性化に資するよう連携を図ることで、これらの状況に対応しています。
産学連携のメリット
では実際のところ、産学連携にはどんなメリットがあるのでしょうか?それぞれの立場から見てみます。
【大学など、研究機関側のメリット】
- 企業と連携して研究を進めることで、企業のリソースや市場知識と研究で得た知識を組み合わせることができ、ノウハウや新技術をビジネスにつなげることができる。
- 民間企業や公的機関から、研究費を調達することができる。
【学生に対してのメリット】
- 企業の現場で行われている開発・研究に触れることができる。
- 職場を体験することで、職業意識や社会性を身につけることができる。
- 学んだことや研究成果が、企業を通じて実際の製品やサービスになる可能性がある。
【企業などの、産業界側のメリット】
- 大学や研究機関の研究者など、その研究分野のスペシャリストをビジネスパートナーにできる。
- 最初から専門知識のある研究者と連携することで、新技術や新商品の開発における貴重なスキルや知見を得られる。
産学連携のデメリット
もちろん産学連携にはデメリットもあります。
【大学など、研究機関側のデメリット】
- 大学側と企業側との間で研究の連携を取ることが難しい。
- 企業側は短期的な成果を求める傾向があるため、長期的なスパンで研究プロジェクトを進めることが難しい。
【学生に対してのデメリット】
- 学術研究よりも実際の製品に関連する研究をする傾向が生まれる
【企業などの、産業界側のデメリット】
- 新たな技術について、企業がノウハウにしたいと考えていても、大学は学会発表したいと考えることがあり、調整が難しい。
- 研究成果について知的財産権を取得する際、大学と企業との間における調整が必要になる。
産学連携に強い大学
次に、産学連携に強い大学のランキングを紹介します。今回紹介するランキングは、経団連、経済産業省、文部科学省で作成した「大学ファクトブック2025」を抜粋してお送りします。
まず、国内外の民間企業からの研究資金等受入額の総額ランキングについて紹介します。
| 順位 | 大学名 | 金額(千円) |
|---|---|---|
| 1位 | 東京大学 | 19,098,494 |
| 2位 | 大阪大学 | 12,568,598 |
| 3位 | 京都大学 | 12,229,812 |
| 4位 | 東北大学 | 8,613,079 |
| 5位 | 名古屋大学 | 5,301,844 |
| 6位 | 東京工業大学 | 4,781,269 |
| 7位 | 慶應義塾大学 | 4,678,596 |
| 8位 | 九州大学 | 4,591,370 |
| 9位 | 順天堂大学 | 3,767,393 |
| 10位 | 北海道大学 | 3,440,727 |
また、国内企業との共同研究実施件数のランキングは次の通りです
| 順位 | 大学名 | 実施件数(件) |
|---|---|---|
| 1位 | 東京大学 | 2,081 |
| 2位 | 東北大学 | 1,493 |
| 3位 | 京都大学 | 1,331 |
| 4位 | 大阪大学 | 1,306 |
| 5位 | 慶應義塾大学 | 874 |
| 6位 | 九州大学 | 835 |
| 7位 | 東京工業大学 | 729 |
| 8位 | 北海道大学 | 717 |
| 9位 | 名古屋大学 | 683 |
| 10位 | 神戸大学 | 661 |
これらのランキングを見ると、産学連携はいわゆる旧帝国大学等の国立大学で、より活発に行われていることが分かります。
また、産学連携の活発な大学は、北海道から九州までの広い地域に分散しているため、地方の企業でも産学連携を行いやすいと言えるでしょう。
産学連携の方法
産学連携の方法としては
- 大学と企業の共同研究
- 大学の教員や研究者による企業への技術・学術指導
- TLO(技術移転機関)による技術移転
があります。
国は「2025年度までに大学・国立研究開発法人に対する企業の投資額をOECD諸国平均の水準を超える現在の3倍とする」という政府目標を設定しています。
そして、この政府目標を達成するため、「産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン」を作成・活用しています。
産学官連携による共同研究強化のためのガイドラインについて:文部科学省
大学と企業の共同研究
大学と企業との共同研究としては、大学と企業が研究目標を共有し、それぞれが研究課題をもって共同して研究する形式(狭義の共同研究)と、大学が企業から研究課題(課題)の提示を受け、研究費用の拠出を受けて研究や調査をし、その成果を企業に報告する方式(受託研究)とがあります。
狭義の共同研究の場合、研究結果に関する知的財産権の所有者は大学と企業の共有となることが多いです。
また受託研究の場合、研究結果に関する知的財産権の所有者は大学と企業の間で協議することが多いです。
関連記事
大学の教員や研究者による企業への技術・学術指導
大学の研究者が企業に対して行う技術指導や学術指導も、産学連携における連携方法のひとつです。
技術指導や学術指導では、大学の研究者が持つ技術やノウハウをもとに企業に対して指導やコンサルティングを行い、企業は指導料を大学に支払います。
TLO(技術移転機関)による技術移転
TLO(Technology Licensing Organization:技術移転機関)による技術移転も、産学連携における連携方法のひとつです。
TLOとは、大学の研究成果や技術などを権利化し、その権利を企業に提供する機関です。
TLOを通じて、企業は研究成果や技術などを知得することができ、その技術移転で得られる収益で、大学は研究資金を獲得することができます。
例:東京大学TLO
産学連携の実例紹介
先ほど国内企業との共同研究実施件数のランキングでも触れたように、大学と企業の共同研究の件数は、上位10大学の合計だけでも10,000件を超えており、非常に活発なことが分かります。
そこで、ここからは産学連携の実例を4件紹介します。
膜関連技術の産学連携
神戸大学では、エネルギーや環境問題など地球規模の課題を膜技術で解決すべく、産学連携や国際連携を軸に、膜工学の研究・教育活動に取り組んでいます。その取り組みの一例として、産官学連携により、膜処理洗浄水設備における膜交換時期を従来の3年から5年に延長した共同研究を紹介します。
この共同研究は、使用済み膜のファウリング物質を解析し、ファウリングを起こしている物質を特定することで、膜の最適な洗浄方法を選定した点に特徴があります。この共同研究は、神戸大学が有するファウリング解析技術と、企業が有する膜処理運転ノウハウと、自治体が有する実設備の運転データを組み合わせて情報を共有することで達成されました。
なおこのプロジェクトは、既存の個別共同研究の繋がりと、神戸大学出身の役員とのコネクションを切り口として、産学連携を実現しています。
温泉トラフグ養殖の産官学連携
温泉トラフグ養殖は、海水の代替となる温泉水「低塩分環境水」と温泉熱の活用により、トラフグを養殖する事業です。
温泉トラフグ養殖は、栃木県那珂川町が地域産業資源の活用による特産品の開発や、6次産業の推進による労働の場の提供を狙いとして行った事業であり、那珂川町から湧き出る温泉の成分が、塩化物泉であることに着目して行った事業です。
温泉トラフグ養殖では、
- 福井県立大学と東京大学の研究室で行われている雌雄判別技術を用いて、白子の生産を効率化する研究
- 宇都宮大学との連携により、性格遺伝子の判別を行い、温厚な親個体から種苗生産を行うことで噛み合いを減少させることを目的とした研究
とが行われました。また、これらの温泉トラフグの養殖・販売にあたって、新たに株式会社夢創造を設立しました。
この温泉トラフグはその後日本各地に広がったものの、養殖や経営の困難さが災いし、那珂川町では現在養殖がおこなわれていないという状況になっています。
那珂川町の「温泉トラフグ」姿消す 業者撤退で 地元に復活望む声 [栃木県]:朝日新聞
農業用ロボットの産官学連携
国立大学法人北海道大学(北大)、岩見沢市、NTT、NTT東日本、NTTドコモも産官学連携協定を締結しています。これは農業機械の自動運転技術に、高精度な位置情報や第5世代移動通信方式(5G)、AI(人工知能)等のデータ分析技術等を活用したスマート農業の実現と、スマート農業を軸とした地方創生・スマートシティのモデルづくりに取り組むためです。
高精度測位・位置情報の取得では、準天頂衛星みちびきを含むGNSS、国土地理院の提供する電子基準点に加え、NTTドコモの提供している「GNSS位置補正情報配信基盤」や統計処理を用いた独自の衛星信号選択アルゴリズムによる検討や検証を行っています。
また自動運転農機のネットワークについては、第5世代移動通信方式(5G)や、Broadband Wireless Access(地域広帯域移動通信アクセス)等の技術を組み合わせ、遠隔監視による無人状態での完全自動走行に求められる、高速・低遅延で信頼性の高いネットワークの実現をめざしています。
さらに、高度情報処理技術およびAI基盤については、自動運転農機等からの映像・画像を含むさまざまなデータを効率的に伝送・圧縮するための高度情報処理技術の検討を行います。
最先端の農業ロボット技術と情報通信技術の活用による世界トップレベルのスマート農業およびサステイナブルなスマートアグリシティの実現に向けた産官学連携協定を締結 | NTT技術ジャーナル
血管病予防に効果を有する食品組成物の技術移転
山口大学は、脳梗塞や心筋梗塞、狭心症等に関わっているとされる「血管の異常収縮」のメカニズムを解明し、魚油に含まれるEPAに抑制作用があることを突き止めました。
しかしながら、従前の機能性食品やEPA製剤は、EPAの立体構造が考慮されておらず血管病抑制効果がかなり弱いという課題がありました。
そこで山口大学では、血管病抑制効果を持つ立体構造を損なわない抽出・精製法について研究し、その抽出・精製法を確立しました。また、加齢による肝機能の低下により、EPAの腸からの吸収が悪くなる場合には、胆汁酸分泌を促す成分を同時に摂取することで、EPAの吸収を大幅に改善することに成功し、EPAの腸からの吸収を高めることに成功しました。
山口大学はこの研究について特許出願をし、特許第5186679号「血管病予防に効果を有する食品組成物」を取得しました。
そしてこの技術をオリエンタルバイオ(株)に移転し、この技術を用いた開発血管病予防機能性食品がオリエンタルバイオ(株)から販売されています。
https://www.tlo.sangaku.yamaguchi-u.ac.jp/wp-content/uploads/2014/10/ttexample-1.pdf
特許事務所に勤務している弁理士です。中小企業のクライアントを多く扱っています。特許業務が主ですが、意匠・商標も扱います。

