働きながら弁理士になる方法について解説します
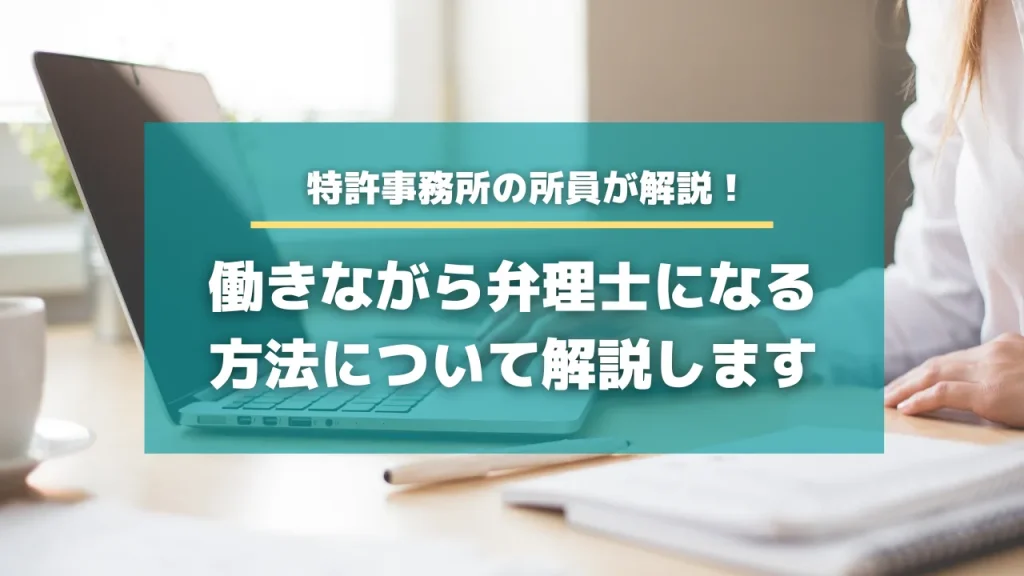
合格者の約9割が社会人
弁理士試験が難易度の高い試験であること、弁理士試験と仕事や家庭との両立が難しいことについては、聞いたことがあると思います。
しかし、弁理士試験に合格した方の約9割は働きながら合格しています。
その一方で、働きながら合格した方の勉強方法については、共通している部分がいくつかあります。
今回は、この共通している部分について、解説していきます。
そもそも、合格に必要な勉強時間は?
弁理士試験に合格するために必要な勉強時間は、約3000時間といわれています。
この3000時間は、論文試験(選択試験)の勉強時間を除いた数字であるため、選択試験を受験する場合には、選択試験の勉強時間がプラスされます。
また、弁理士試験のうち短答試験(一次試験)に合格するまでの勉強時間は、約2000~2500時間といわれています。
その一方で、論文試験・口述試験に合格するまでの勉強時間は、約500~1000時間といわれています。ちなみに特許法・実用新案法・意匠法・商標法については、勉強する箇所の大半が短答式試験と論文式試験で重複しています。
- 短答試験の勉強…約2000~2500時間
- 論文試験・口述試験の勉強…約500~1000時間
- 弁理士試験の勉強(トータルの時間)…約3000時間
弁理士試験に合格するまでのスケジュールは?
ここからは、弁理士試験に合格するまでのスケジュールを大雑把に求めてみます。
2年間で弁理士試験に合格することを目標とした場合、1年間で1500時間、1週間で30時間の勉強時間を確保する必要があります。この場合には、月~金曜日は毎日3時間、土日で合計15時間の勉強時間というスケジュールが考えられます。
また、3年間で弁理士試験に合格することを目標とした場合、1年間で1000時間、1週間で20時間の勉強時間を確保する必要があります。この場合には、月~金曜日は毎日2時間、土日で合計10時間の勉強時間というスケジュールが考えられます。
こちらのアンケートを見てみても、合格している方の多くが、先程のスケジュールに近い勉強時間を確保していることがうかがえます。
勉強時間はどう確保する?
弁理士試験に合格するためには、平日にも最低2時間の勉強時間を確保する必要があります。
しかし仕事や家庭の事情で、机に向かう時間がなかなか取れない方もいると思います。
そのため勉強時間を確保するには、スキマ時間の活用が重要になります。例としては、通勤中に受験機関の講義を聞くとか、入浴中に暗記をする、とかいったことが挙げられます。
とりわけ聴覚を利用した勉強は、歩いている時でも可能なためかなり重宝します。
筆者自身の勉強方法は…
ちなみに筆者の場合は、電車通勤時に条文の読み込みを行い、歩いているときに暗記事項を吹き込んだICレコーダーを聞いていました。
また休日のように、まとまった時間が取れるタイミングでは、どうしても時間のかかる勉強を優先的にするのが良いと思います。
具体的には、法律で規定されている手続きの流れや立法趣旨などを理解する勉強や、テスト(答練)を受けることなどですね。
ただし、まとまった時間を確保するためには、家族の協力が必要。できればあらかじめ家族と、勉強時間の確保について相談することをおすすめします。
選択試験の免除で、負担を減らそう
弁理士試験においては、選択試験の免除により負荷をなくすということも、重要な戦略となります。
まずは、弁理士試験の日程をご覧ください。
- 短答試験:5月中旬~下旬
- 論文試験(必須):6月下旬~7月上旬
- 論文試験(選択):6月下旬~7月上旬(概ね、論文試験必須科目の3週間後)
- 口述試験:10月中旬~下旬
選択試験を受験する場合、必須科目の試験勉強で全力疾走した直後に、さらに試験勉強をすることになります。実情としても、選択試験は、論文の必須科目試験の3週間後に行われるため、準備が十分にできません。
事実、弁理士試験は、最終合格者の8割以上が選択試験免除者となっています。
ちなみに弁理士試験の最終合格者のうち、約半数は修士・博士資格により選択試験を免除されています。情報処理系の資格による選択試験免除者も多いです。
勉強を継続するには?3つのコツ
弁理士試験の試験勉強は、短期合格者でも2年から3年かかり、人によってはそれ以上かかることも珍しくありません。
試験勉強を続けていくにあたっては、調子の出ない時期や、気分の優れない時期も生じます。そのため、勉強を継続するためには、モチベーションの維持も重要になります。
受験勉強仲間を作る
試験勉強を継続するための重要な要素の一つが、勉強仲間を作ることです。自分一人では、どうしても勉強時間が少なくなり、勉強が思うように進まない、ということがよく起こります。
受験機関の講義やゼミを通学受講している場合には、これらの受講を通じて比較的かんたんに知り合うことができます。また最近では、SNSを通じて、受験仲間を作ることも多いです。
定期的にテスト(答練)を入れる
定期的に行われるテスト(答練)も、試験勉強を続けるためのモチベーションになります。
テスト前になると勉強の集中力が上がる、という経験は皆さんもあると思いますが、これは試験勉強においても同じです。
ですので、小テスト形式でもいいので、週1回くらいのペースでテストを入れることも、モチベーションの維持に有効な方法です。
自分へのご褒美を用意
試験勉強中は、自分を追い込むことがどうしても多くなります。
そのため、勉強時間を確保することのできる範囲で、定期的にご褒美を用意することも、モチベーションの維持に重要です。
ただし、ご褒美の内容としては、長時間かからないものとすることが重要になります。なお筆者は受験勉強中、日曜夜にスポーツをすることを自分のご褒美にしていました。
試験合格後の実務修習も、働きながら受けられる
試験合格後の実務修習には、講義の受講と、起案の提出、そしてeラーニングの受講があります。講義については、平日夜に受講するコースや、土曜日に受講するコースも用意されています。
実務修習では、弁理士試験の受験時と同様に、平日は毎日2~3時間、土日で10時間程度の勉強時間が必要となります。
しかしながら、働きながら弁理士試験に合格した方であれば、実務修習も働きながら受けることは可能です。
【弁理士解説!】受験生必見の弁理士試験を攻略するコツ シリーズ一覧
- 目安の勉強時間は?弁理士試験攻略のコツ
- 弁理士試験に独学で合格できる?
- 弁理士試験の難易度は?攻略のポイント
- 弁理士試験対策のおすすめ参考書9選+選び方のコツ
- 弁理士試験の短答試験に合格するためには?
- 【弁理士試験】論文式試験の有効な対策法は?勉強方法を紹介
- 【弁理士解説】弁理士試験の最終関門「口述試験」を突破するポイント
- 弁理士になるための最終関門 実務修習について
特許事務所に勤務している弁理士です。中小企業のクライアントを多く扱っています。特許業務が主ですが、意匠・商標も扱います。

