弁理士試験の難易度は?攻略のコツ
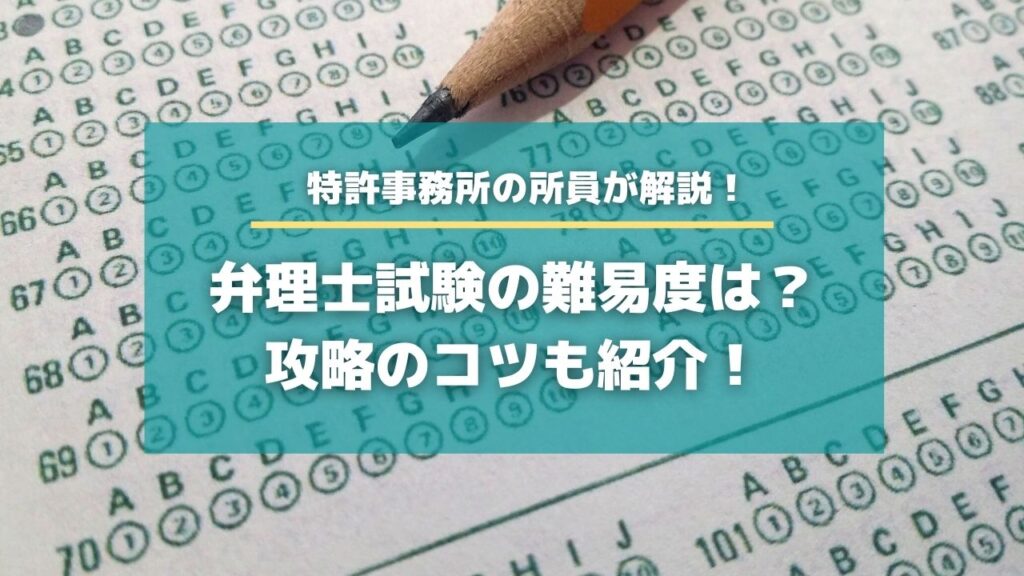
結論から言えば、弁理士試験の難易度は、国家資格のなかでもかなり高いものです。
弁理士試験の難易度について、データもあげながら紹介します。
なお記事の最後には【弁理士解説!】受験生必見の弁理士試験を攻略するコツシリーズの一覧も掲載しているので、ぜひラストまでお読みください。
弁理士試験は難易度が高い
合格のハードルが高いと言われる弁理士試験ですが、どれほど難しいのでしょうか。
参考:令和6年度弁理士試験統計
合格率から見る難易度
令和6年(2024)年の弁理士試験の合格率は6.0%です。
志願者数(※実際の受験者数ではありません)は3,502人、最終合格者数は191人でした。
合格率6.0%というと、100人受験して6人しか受からない計算ですから、非常に狭き門であることがイメージできると思います。
必要な勉強時間から見る難易度
弁理士試験合格に必要な勉強時間は約3,000時間と言われています。
3,000時間というと、1日2時間勉強するとすれば1,500日(約4.1年)、1日4時間勉強するとしても750日(約2年)、かかる計算です。
仕事をしながら受験することを考えると、なかなかハードルは高そうです。
なお難易度が高いと言われる国家資格合格に必要だとされる勉強時間は、以下の通り。
- 弁理士 3,000時間
- 弁護士 3,000~8,000時間
- 公認会計士 4,000時間
- 司法書士 3,000時間
- 税理士 3,000時間
- 土地家屋調査士 1,000〜1,500時間
- 中小企業診断士 1,000時間
- 社会保険労務士 800〜1,000時間
- 行政書士 500〜1,000時間
関連記事
平均受験回数
令和6年(2024)年の弁理士試験の最終合格者の、平均受験回数は2.41回でした。初回での合格、つまり1発合格者は29人いました。
平均2.41回というと、3年弱も試験を受け続ける計算ですね。マインドやモチベーションを維持するのも大変なことが想像できます。
そこで、短期合格の秘訣についても後で触れたいと思います。
他の国家資格と比べても難しい?
上であげた国家資格別に、合格率を見てみたいと思います。
- 弁理士 6~10%
- 弁護士 22~39%
- 公認会計士 9~11%
- 司法書士 3~4%
- 税理士 12~15%
- 土地家屋調査士 7~9%
- 中小企業診断士 3~8%
- 社会保険労務士 4~6%
- 行政書士 8~15%
合格率だけで見れば、弁理士試験よりも低いものもありますね。ただ、弁理士試験の最終合格者の総数は他の試験と比較して相対的に少なく、やはり「狭き門」であるイメージが高いです。
関連記事
士業の難易度を徹底比較!8士業をランキング形式で紹介します!
弁理士試験には免除制度がある
弁理士試験には試験の免除制度があります。短期合格を狙うなら、免除制度をうまく活用したいところです。
一次試験(短答試験)の免除
一次試験(マークシート式の短答試験)は3つの条件いずれかに当てはまれば免除申請が可能です。
①短答試験の合格者
一次試験に合格した場合、合格の日から2年間、同試験が免除されます。一度合格すれば、次の2年度分(試験2回分)は受験しなくてもよくなるわけです。3年度以降は、再受験が必要になります。
②工業所有権に関する科目の単位を修得し大学院を修了し、工業所有権審議会の認定を受ける
工業所有権審議会から認定を受けた人は、大学院を修了した日から2年間、「工業所有権に関する法令」と「工業所有権に関する条約」に関する試験科目が免除されます。
著作権法及び不正競争防止法の試験科目のみ受験する形ですね。
③特許庁において審判又は審査の事務に5年以上従事した人
特許庁にて審判官または審査官を5年以上勤めた人も、「工業所有権に関する法令」と「工業所有権に関する条約」に関する試験科目が免除されます。
二次試験(論文試験/必須科目)の免除
二次試験には、必須科目と選択科目とがあります。必須科目については一次試験と同様で、合格すると合格の日から2年間、同試験が免除されます。
特許庁で審判官または審査官を5年以上勤めた人が、試験を免除されるのも一次試験と同じです。
二次試験(論文試験/選択科目)の免除
選択科目は一度合格すれば、永続的に免除されます。
また修士・博士・専門職学位に基づく選択科目免除資格認定を受けた方も永久に選択科目が免除されます。
特許庁が指定する他の公的資格を有する人も、同様に選択科目の永久免除が可能です。
めざせ一発合格!弁理士試験を短期合格する秘訣【弁理士直伝】
ここでは、短期合格の秘訣についてポイントを紹介します。正しく効率的な勉強を行えば、1発合格も決して難しいことではありません。
試験の全体像を把握する
まずは慌てず騒がず、 受験範囲、受験科目の全体構造を眺めて把握することです。具体的には、知的財産法全体の枠組み・法律の構造を押さえます。
どういうことか、具体例とともに見ていきましょう。
知的財産法とは特許法、実用新案法、意匠法、商標法などの総称。特許法といった法律は、法体系の枠組みでは「特別法」と言われます。
対して憲法、民法などは一般法と呼ばれています。
特許法は、民法などの一般法における特別法であり、特別法は一般法より適用される優先度が高いです(特別法優先の原則)。
上位の法律から、憲法>民法・民事訴訟法>知的財産法>特許法、といった感じになりますが、例えば憲法は財産権の細部までを規定しているわけではありません。
特別な事象についてより具体的に規定したのが特別法で、そのため特別法が一般法に優先して適用されるわけです。
このように、法律構造全体をしっかり理解することで、個別の条文の位置付けや意義が理解しやすくなります。
条文の趣旨(成立背景)を理解する
条文には必ず成立背景があります。このような規定を設けないと何かしら不都合や困ることがあった、だから条文が規定された、といった事情があるのです。
条文の成立背景を理解することで条文を覚えやすくなりますし、見たこと、聞いたことのない事案や問題にあたった場合でも、条文の成立背景に立ち返ることで回答に辿りつけることも少なくありません。
過去問を最低3回まわす
試験対策としては、やはりなんといっても過去問をこなすことです。
過去問で問われていることは、専門家として理解しておかないといけない重要なポイントです。
過去問は少なくとも過去3年分、できれば4~5年分は解いておきたいところです。
なお弁理士試験の過去問は、問題集が多く出されていますので、上手に活用してください。
一度解いて、正答となる理由も含めて説明・回答ができた問題については、再度解く必要はありません。間違えたところ、説明ができないところを中心に、説明ができるようになるまで何度も回しましょう。
少なくとも3回はまわし、理解が浅いところは、3回と言わず何度でも解き直しましょう。
最後までやり抜く秘訣3つ
弁理士試験合格までは平均して数年と、なかなかに長い道のりです。最終合格までやり抜く秘訣について紹介します。
1.環境に頼る
環境というのはとても大事です。例えば最近では、テレワークも当たり前になっていますが、自宅で仕事をするのと、出勤して仕事をするのとで、同じようにこなせるでしょうか。(同じようにこなせるのであれば問題ありませんが)
勉強も同じで、やはり、勉強に適した環境で勉強する、ということは重要です。勉強に特化した環境だとより集中して勉強できるものです。
その点では、受験機関の教室などを活用すると良いでしょう。
周りは受験生だけ、皆、試験合格に向けて勉強している、という環境であれば、逆になまけてしまうことのほうが難しくなります。
2.勉強仲間を作る
1人で勉強することは孤独で、モチベーション維持も難しくなります。勉強のペースもつかみづらくなってしまいます。
そこで勉強仲間がいれば、きっと、勉強のペースメーカーになってくれます。
また勉強仲間との比較で、自身の現在のレベルも分かります。
さらに、勉強仲間と議論することで理解も深まるでしょう。やはり、アウトプットすることは何にも増して重要です。アウトプットすることで頭に定着します。
ぜひ、勉強仲間を見つけてください。講座に通ったり、SNSで探したりすれば比較的簡単に仲間が見つかるはずです。
3.完璧を求めすぎない
勉強の計画が完璧に進むことは素晴らしいことですが、人間、100%完璧にこなすことは難しいですね。
多少計画通りに進まなくても、卑下せず、リラックスして考えましょう。
「計画の8割も達成できれば全然十分!」くらいの考え方のほうがうまく進みます。
まとめ
弁理士試験の難易度について見てきました。
弁理士試験は、合格率も低く、最終合格者数も相対的に少ない試験であり、難易度が高い試験の一つです。
ただし、かといって合格できない試験では決してなく、短期合格も十分可能な試験です。
この記事や下のシリーズ記事なども参考に、ぜひ頑張ってください。
【弁理士解説!】受験生必見の弁理士試験を攻略するコツ シリーズ一覧
- 目安の勉強時間は?弁理士試験攻略のコツ
- 弁理士試験に独学で合格できる?
- 弁理士試験の難易度は?攻略のポイント
- 弁理士試験対策のおすすめ参考書9選+選び方のコツ
- 弁理士試験の短答試験に合格するためには?
- 【弁理士試験】論文式試験の有効な対策法は?勉強方法を紹介
- 【弁理士解説】弁理士試験の最終関門「口述試験」を突破するポイント
- 弁理士になるための最終関門 実務修習について
知財専門の求人サイト「知財HR」
知財業界はいわゆるニッチ業界。そこで転職時に重要になってくるのが「どれだけリアルな情報を集められるか」です。
知財HRではそんなお悩みにこたえるべく、求人票にインタビューを掲載中!(※求人によります)
一歩踏み込んだ仕事内容、職場の雰囲気、求人募集の背景など…。たくさんのリアルな情報を知ったうえで求人へ応募できるんです。求人検索は下のボタンから↓↓↓
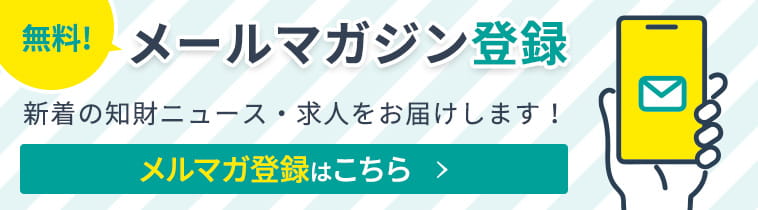

エンジニア出身です。某一部上場企業にて半導体製造装置の設計開発業務に数年携わり、その後、特許業界に転職しました。
知財の実務経験は15年以上です。特許、実用新案、意匠、商標、に加えて、不正競争防止法、著作権法、など幅広く携わっています。
諸外国の実務、外国法にも長けています。

