弁理士になるためのルートを解説します
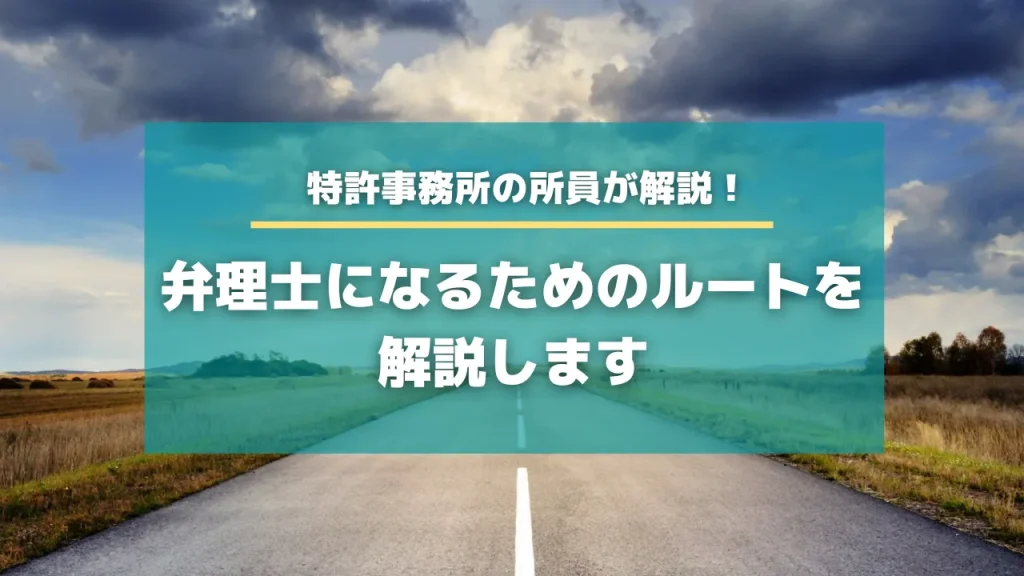
弁理士になるためのルートとしては、弁理士試験に合格するルートのほか、特許庁の審査官に従事するルートと、司法試験に合格し司法修習を終了するルートがあります。またいずれのルートを通る場合でも、実務修習を受けなければ弁理士登録をすることはできません。
今回は、この3つのルートと実務修習、そして登録の手続きについて解説します。
弁理士になる道は3つ
弁理士になる道は、
- 弁理士試験に合格するルート
- 審査官に従事するルート
- 司法試験に合格し、司法修習を修了するルート
の3つがあります。しかしこれから弁理士を目指す際には、ほとんどの方が弁理士試験ルート、もしくは審査官従事ルートを選択することになると思われます。
弁理士試験ルート
弁理士試験ルートは、弁理士を目指す方の大半が選択する道です。
弁理士試験は、2~3年で合格することも可能ですが、5年以上かかっても合格できない方もいる、という特徴を持つ試験です。
そのため受験機関などを積極的に使用して、効率よく勉強することが、短期合格には重要となります。
概要【受験資格・難易度】
弁理士試験は1年に1回行われます。
弁理士試験には、短答式筆記試験、論文式筆記試験(必須科目、選択科目)、口述試験があり、全ての試験に合格することで、最終合格となります。
ただし、短答式筆記試験と論文式筆記試験(必須科目)は合格することで、その後2年間は合格した試験について受験が免除されます。また論文式筆記試験(選択科目)は、1回合格することで、翌年以降の選択科目の試験は免除されます。
弁理士試験には受験資格はなく、学歴や年齢に関係なく受験可能です。
弁理士試験の難易度は、他の国家資格と比較しても高い方であり、司法書士や公認会計士と同程度の難易度といわれています。弁理士試験に合格するための勉強時間の目安はおおむね2000時間から3000時間と言われています。
短答式筆記試験
短答式筆記試験は、例年5月後半に行われています。
短答式筆記試験はマークシート式の試験です。問題数は60問であり、①特許・実用新案法20問、②意匠法10問、③商標法10問、④条約10問、⑤著作権・不正競争防止法10問です、また、試験時間は3時間30分です。
合格点はここ数年39点となっています。また、先ほどの①から⑤の教科のうち、1教科でも正答率が4割未満である場合には、不合格となります。
論文式筆記試験
論文式筆記試験には、必須科目と選択科目があります。必須科目は例年7月初めに行われています。また、選択科目は例年7月後半に行われています。
必須科目
必須科目の試験科目は、特許法・実用新案法、意匠法、商標法です。
特許法・実用新案法の試験時間は2時間、意匠法と商標法の試験時間はいずれも90分です。
配点は、許法・実用新案法は2問で200点、意匠法と商標法は1問で100点です。
必須科目は、4問の平均点が54点以上であり、かつ、47点未満の科目がないことで、合格となります。
選択科目
選択科目の試験科目は、理工系と法律系があり、いずれか1科目を選択します。選択科目の試験時間は90分で、配点は100点です。
選択科目は60点以上を取ることで合格となります。
選択科目免除
選択科目については、所定の資格を有しているか、又は選択科目に関する修士・博士の学位を有することで、試験を免除されます。
免除の対象となる資格については細かく規定されていますが、主な資格としては、行政書士や薬剤師、情報処理技術者試験などがあります。
口述試験
口述試験は例年10月後半に行われます。
口述試験の試験科目は、特許法・実用新案法、意匠法、商標法です。また、試験時間は、いずれの科目も10分です。
口述試験では、採点基準がA、B、Cの3段階となっており、C評価の科目が2科目以上ない場合に合格となります。
特許庁事務従事ルート
特許庁事務従事ルートは、特許庁において審判官又は審査官として従事した期間が通算して7年以上である方は、実務修習を受けることで、弁理士になることができるという道です。
そして審判官、審査官になるには
- 国家公務員の試験に合格して特許庁に勤務するルート
- 任期付審査官の試験に合格して特許庁に勤務するルート
があります。
ただし多くの方は、まず審査官補として採用され、3~4年後に審査官になるため、実際には10年前後特許庁事務に従事することになります。
弁護士資格ルート
弁護士資格ルートは、司法試験に合格し司法修習を終了した方が、実務修習を受けることで、弁理士になることができるルートです。
このルートで弁理士になる方の多くは、既に弁護士としての業務をしている中で、知財関係の業務をするため、弁理士登録もする、というパターンです。
弁理士資格を得たあとにすること【実務修習・登録】
弁理士資格を得たあと、弁理士登録をするために必要なこととしては、実務修習と、弁理士登録の手続きがあります。
実務修習と弁理士登録の手続きは、弁理士試験ルート、特許庁事務従事ルート、弁護士資格ルートのいずれの場合でも必要になります。
実務修習
実務修習は、特許、意匠、商標における出願書類や補正書・意見書を作成したうえで講義を受講したり、知的財産権全般の講義をe-ラーニングで受講をする修習です。
実務修習の申し込み期間は例年11月中旬です。弁理士試験の最終合格発表から実務修習の申し込み期限までは期間が短いため、期間の徒過などに注意する必要があります。また、申し込みの際の費用は118,000円です。
出願書類や補正書・意見書の作成については、所定の期限までに提出する必要があります。また、e-ラーニングの受講時間は約70時間です。
弁理士登録
実務修習が修了すると、弁理士登録をすることが可能となります。弁理士登録時に必要な書類は多数にわたるため、日本弁理士会のホームページ等を参考にして書類をそろえる必要があります。
また、弁理士登録時に必要な費用は、110,800円です。
【弁理士解説!】受験生必見の弁理士試験を攻略するコツ シリーズ一覧
- 目安の勉強時間は?弁理士試験攻略のコツ
- 弁理士試験に独学で合格できる?
- 弁理士試験の難易度は?攻略のポイント
- 弁理士試験対策のおすすめ参考書9選+選び方のコツ
- 弁理士試験の短答試験に合格するためには?
- 【弁理士試験】論文式試験の有効な対策法は?勉強方法を紹介
- 【弁理士解説】弁理士試験の最終関門「口述試験」を突破するポイント
- 弁理士になるための最終関門 実務修習について
特許事務所に勤務している弁理士です。中小企業のクライアントを多く扱っています。特許業務が主ですが、意匠・商標も扱います。

