弁理士とは?仕事内容から働き方まで徹底解説!
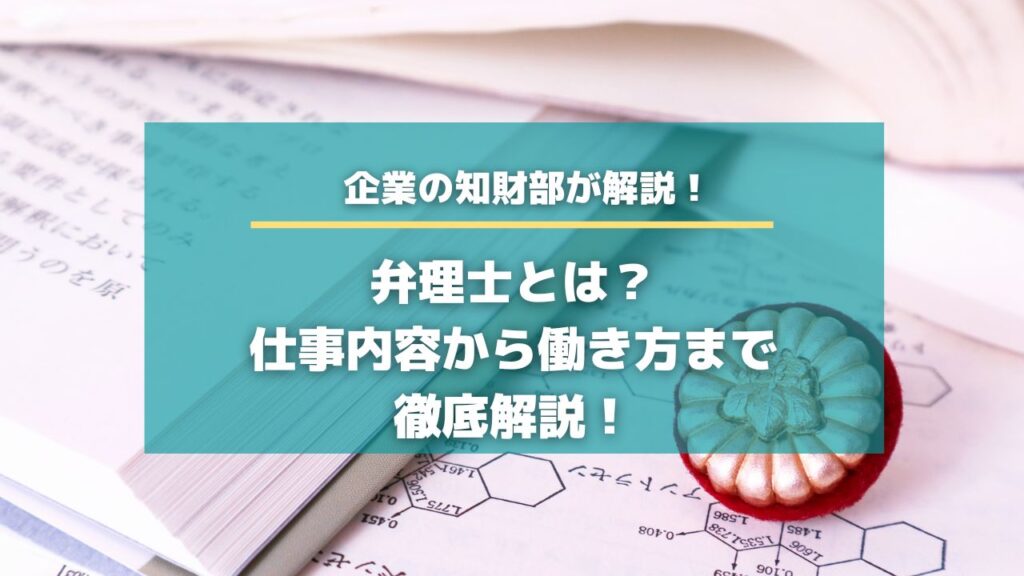
弁理士は特許をはじめとした知的財産権に関わる、専門性の高い仕事です。
法律を取り扱う、業務の難易度が高いお堅い仕事というイメージを持っている人も少なくないでしょう。
実際は、法律だけでなく様々な知識やスキルを活かせる仕事であり、働き方も多岐に渡ります。
本記事では、弁理士の仕事内容や就職先、年収、向いている人などをまとめました。
目次
弁理士とは、どんな職業?仕事内容は
弁理士とは、「特許・実用新案・意匠・商標に関する手続の代理または鑑定を業とする者(引用:精選版 日本国語大辞典)」のこと。簡単にいうと、知的財産のプロフェッショナルです。
また「理系の弁護士」とも称されるほど、高い科学知識・法律知識を有します。
弁理士の仕事は、「知的財産の権利化」「知的財産に関する紛争解決」「知的財産の活用支援」の三つに大別できます。
知的財産の権利化
弁理士は知的財産(特許、実用新案、意匠、商標)の出願・権利化を行います。特許庁へ行う出願・権利化の手続きは弁理士のみができる業務です。
出願した内容がこれまでにない発明やデザインなどであると権利化され、独占的な使用が認められます。
ここで特徴的なのが、知的財産以外の専門技術に関しても勉強しながら仕事を進める点。
出願手続き上の不備がないように書類を作るだけなら、知的財産や法律の知識のみで十分でしょう。
しかし新しいアイデアを権利化するためには、発明に関する技術にも詳しくなければならないのです。ですから弁理士はそれぞれ、化学、機械、IT・ソフトウェアなどの得意分野を持っています。
知的財産に関する紛争解決
特許権の侵害といった、知的財産に関する紛争の事前回避・問題発生時の解決も弁理士の仕事です。ときには弁護士とも協力しながら、知的財産の知識や交渉力を活かして対応します。
- 権利化した特許権が無効となる
- 訴訟を起こした企業に損害賠償金を支払う
などを避けるために、弁理士が解決策を検討します。
任天堂とコロプラの訴訟のように、賠償金が億単位に及ぶこともあるため、弁理士の仕事は企業の存続を支える重要な仕事とも言えるでしょう。
知的財産の活用支援
取得した権利の活用をサポートしたり、知財面からのコンサルティング業務を行ったりといった、知的財産の活用を支援するのも弁理士の仕事のひとつ。
- 知財戦略の策定支援
- 知財コンサルティング
- 発明発掘支援
- M&Aの際の知財DD
- ライセンス契約関連業務
など、知財を使った利益創出についての提案を行います。
弁護士との違い
弁理士と弁護士は名前が似ていますし、両方国家資格です。そんな両職種の違いは、対応可能な業務範囲の広さにあります。
弁理士は、知的財産および知的財産法に特化した専門家です。請け負う仕事は、知的財産の権利化がメイン業務となります。
一方の弁護士は法律問題全般に対応可能です。企業法務から民事事件、刑事事件まで請け負えます。また弁護士法により、弁護士資格保持者は弁理士の仕事を請け負うことが可能です。
第三条 弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。
2 弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。
引用: 弁護士法 | e-Gov法令検索
関連記事
弁理士になるメリット
弁理士になるメリットとしては
- 一般的なサラリーマンより高年収
- 世界的に仕事が増えている
- 自由度が高く、ワークライフバランスがとりやすい
- 60代以上でも活躍できる
ことが挙げられます。
知的財産は年々注目度の高まっている分野です。なおかつ専門性の高い職業なので、高年収が見込めたり60代以上になっても活躍できたりします。
弁理士に向いている人
- 出願の依頼人や特許庁とのコミュニケーション能力
- 新しいことを学び続ける好奇心
- 仕事のスピードと丁寧さのバランス感覚
などを持っている人が弁理士の仕事に向いています。
出願内容を正確に判断するためには、案件ごとにその分野における技術常識を理解しなければなりません。そのための勉強を続けられる、知的好奇心が弁理士の仕事には求められます。
そして弁理士の仕事をこなすには、スピードと丁寧さのバランス調整も欠かせません。
まず実際の出願書類は、以下のステップを踏んで作成されます。
- 発明に関する技術を学ぶ
- 公開されている情報を調査する
- 出願書類を作成する
ここで曲者になるのが、公開されている情報の調査です。年間30万件ほど公開されているすべての特許に発明の内容が記載されているかを調べていては、月に1件の出願書類を作るのも難しいでしょう。
発明の要点を見極め調査する文献を限定し、与えられた時間で対応しなければなりません。
時には1ヶ月に10件の出願書類を作る過密スケジュールをこなす場合もあるようです。
関連記事
どんな人が弁理士(知財業界)に向いている?現役弁理士が話します
弁理士としての働き方【年収・将来性】
弁理士として就職したらどんな風に働いていくのか。年収や将来性といった部分を見ていきましょう。
弁理士の年収
まず特許事務所に勤める弁理士の年収は、平均700万円程度と言われています。
ただし多くの特許事務所は成果主義(歩合制)を採用していることもあり、下は200万円台から上は1000万円オーバーまでと、能力やポジションによって年収の差が大きく開きます。
| ポジション | 年収の目安 |
|---|---|
| 雇われ弁理士 | 600万円台 |
| パートナー弁理士 | 700万円〜1,000万円超 |
| 代表弁理士(中規模事務所) | 1,000〜2,000万円 |
続いて企業知財部に所属する場合の弁理士の年収を紹介します。
| ポジション | ポジション |
|---|---|
| 実務担当者・新卒〜5年目 | 〜500万円 |
| 実務担当者・5年目〜 | 500万円〜1,000万円 |
| 管理職・課長 | 1,000万円〜1,200万円 |
| 管理職・部長 | 1,200万円〜 |
なお会社の規模などによって年収は変わるので、参考程度にご覧ください。
実際知財業界で働くと給料がいくらになるか知りたい人は、求人一覧を見てみても良いでしょう。
関連記事
弁理士はオワコン?将来性について
ネットなどでは「弁理士の業務は将来AIが担うことになり、仕事がなくなる」と言われていますが、弁理士は将来性がある仕事と言えます。
これは
- 今後も技術が進歩するたびに知的財産権の出願・権利化が行われる
- 企業のグローバル化に伴い外国への出願や知的財産権の紛争が増える
といった予想がされるためです。
また訴訟や交渉などの業務はAIによる代替が難しいのも、将来性の見込める理由のひとつです。
関連記事
弁理士になるには、国家資格の取得が必要【弁理士試験の概要】
弁理士になりたい!
そのためには、弁理士試験への合格が必要です。
国家試験の中でも難易度が高い資格であり、取得に数年をかける人も少なくありません。
弁理士試験の詳細について、解説します。なお記事の一番下に【弁理士解説!】受験生必見の弁理士試験を攻略するコツ シリーズのまとめ一覧があるので、こちらもぜひチェックしてください。
弁理士試験の日程・受験料・会場(2025年/令和7年度)
2025年度の弁理士試験の概要はこちらの通り。
【申込スケジュール】
- インターネットでの願書請求…2025年2月3日~3月21日
- 郵送での願書請求…2025年3月3日~3月21日※消印有効
- 窓口での願書請求…2025年3月3日~3月31日(9時~17時)
- 願書受付期間…2024年3月6日~4月3日※消印有効
【受験スケジュール】
- 短答試験…2025年5月18日
- 短答試験合格発表…2025年6月9日
- 論文試験(必須科目)…2025年6月29日
- 論文試験(選択科目)…2025年7月27日
- 論文試験合格発表…2025年9月24日
- 口述試験…2025年10月18日~20日のいずれかの日
- 最終合格発表…2025年11月10日
【受験料】
- 一律12,000円(特許印紙にて納付)
【試験会場】
- 短答試験…東京、大阪、仙台、名古屋、福岡
- 論文試験…東京、大阪
- 口述試験…東京
なお具体的な試験会場は、官報および特許庁のHPで公開されます。
弁理士試験の内容・科目
短答試験
- 全60問の5肢択一式マークシート形式
- 所要時間は3時間30分
短答試験では正確な知識が問われます。
試験範囲は、特許・実用新案法、意匠法、商標法、工業所有権に関する条約、著作権法・不正競争防止法となります。問題数は特許・実用新案法が20問、ほかは10問です。
論文試験
- 全4科目の記述式試験
- 所要時間は合計6時間30分(必須科目5時間、選択科目1時間30分)
論文試験では試験官が採点するので、だましが聞きません。十二分に対策して臨む必要があります。
試験範囲は、必須科目が特許法・実用新案法、意匠法、商標法の3つです。
選択科目は理工I(機械・応用力学)、理工II(数学・物理)、理工III(化学)、理工IV(生物)、理工V(情報)、法律(弁理士の業務に関する法律)のうちひとつを選んで受験します。
口述試験
- 全3科目の面接方式
- 各科目10分程度(トータル30分程度)
口述試験の試験範囲も、特許法・実用新案法、意匠法、商標法の3つです。
面接形式ということで、知識以外の、コミュニケーション能力なども問われることになります。
弁理士試験の免除制度
弁理士試験には免除制度があります。初受験から利用できる免除条件もあるので、短期合格を目指す場合は利用を検討していきましょう。
【短答試験】
- 短答試験合格者(合格日から2年、短答試験が免除)
- 工業所有権に関する科目の単位を修得し大学院を修了した者で、工業所有権審議会の認定を受けた者
- 特許庁において審判または審査の事務に5年以上従事した者
【論文試験(必須科目)】
- 論文試験(必須科目)合格者(合格日から2年、論文試験(必須科目)が免除)
- 特許庁において審判または審査の事務に5年以上従事した者
【論文試験(選択科目)】
- 論文式筆記試験選択科目合格者(一度合格すれば永続的に免除)
- 修士・博士・専門職学位に基づく選択科目免除資格認定を受けた者
- 特許庁が指定する他の公的資格を有する者(行政書士など)
【口述試験】
- 特許庁において審判または審査の事務に5年以上従事した者
難易度はどれくらい?合格率と勉強時間
弁理士試験の難易度は国家資格の中でも高く、平均合格率は5〜10%です。試験合格に必要な勉強時間は3,000時間とも言われています。
数年かけて合格する人がほとんどで、令和6年度は最終合格者の平均受験回数が2.41回となっています。
特許事務所にて特許技術者として働きながら実務経験を積んで、弁理士資格の取得を目指している人も多くいます。
>>特許技術者として転職後に弁理士試験に合格した人の体験談を読む
独学で弁理士試験に合格できるのか
可能か不可能か、で言えば独学でも弁理士試験合格は可能です。とはいえ弁理士試験は難易度が高いので、LECやTACのような予備校に通うのが無難ではあります。
もしも独学合格を目指す場合、向いているのは以下のような人。これまでの経験が活きるでしょう。
- 法律の基礎知識がある人
- 知財の実務経験がある人
- 他の難関資格の合格経験がある人
逆に完全初学者や実務経験のない人にとって、知的財産法の構造や細部は難解なので、予備校に頼ったほうがいいでしょう。
関連記事
弁理士試験に合格したあとの流れ
ここからは、弁理士試験に合格したあとの流れを簡単に紹介します。
1.実務修習を受ける
まずは実務修習という研修を受けます。これは弁理士になるための最終関門で、弁理士にとって必要な能力を備えていることを担保するために行われます。
実務修習は弁理士試験の最終合格発表のすぐあとから申込が始まり、12月~2月にかけて研修を受けていきます。
関連記事
2.弁理士登録をする
実務修習に合格すると、弁理士登録ができるようになります。「弁理士」として働いて独占業務をするためには、弁理士登録をしなければいけません。
弁理士登録をするときには、日本弁理士会に書類を郵送提出します。
関連記事
3.転職先・就職先を探す
弁理士になると、担当できる仕事の幅が広がります。弁理士試験合格を機に転職する人も少なくありません。
知財HRには未経験OKの求人も多数掲載中!また求人詳細と併せて職場の特徴をインタビュー形式で紹介しているので、「どんな風に働くか」を具体的にイメージすることができます(一部求人を除く)
弁理士の勤務先はどこ?
弁理士の就職先は特許事務所や企業の知的財産部が主ですが、その他に特許庁や知財コンサルティング業を行う職場で働く人もいます。
特許事務所
特許事務所は、弁理士の就職先の代表例です。主な仕事は、企業から依頼された特許、実用新案、意匠、商標の出願・権利化になります。
特許事務所の規模は数名〜数百名と様々であり、規模に応じて、事務所が受け付けている仕事の種類や個人の担当する業務範囲が異なります。
関連記事
企業の知的財産部
特許事務所の次に多い弁理士の就職先が、企業の知的財産部です。日本の弁理士のうち、約25%が企業内弁理士として会社勤めをしています。
企業に所属していると、研究開発や経営企画などを担当する部署の仕事に関わることが少なくありません。研究開発者の実験データに直接触れて発明を発掘することなどは、企業でなければ経験できないでしょう。
また企業の知財部員は、製品の開発業務を兼任していたり、これらの関連部署へ異動したりする場合もあります。
関連記事
そのほか特許庁や調査会社、大学など
ほかにも弁理士の就職先として以下が挙げられます。それぞれの職場で弁理士が担当する仕事内容も簡単に紹介します。
- 特許庁…企業や特許事務所による特許出願の審査などを行う
- 調査会社…依頼を受け、侵害予防調査や無効資料調査などの各種調査を行う
- 知財コンサルティング…知的財産権を活かした経営について、クライアントへアドバイスする
- 大学・研究機関…研究成果の活用方法を検討し、産学連携を促進する
なお知財コンサルティングや大学研究機関に勤める弁理士は、日本の弁理士の1%未満であり、特許事務所や企業での勤務経験のある人がほとんどです。
関連記事
「審査官は、出願人と一緒に特許を創る相手」特許庁審査官・平井隼人氏【インタビュー】
未経験でも弁理士試験合格・転職は可能か
まず全くの知財初心者でも、弁理士試験の合格は可能です。ただし法律の基礎知識や実務経験に基づく知識などがない分、合格までの道のりは大変になります。
可能なら弁理士講座を受講して試験合格を目指すのが良いでしょう。
無事に弁理士試験に合格したあとも、別業界から知財業界へ転職することに不安を感じる人がいるかもしれません。
知財業界は比較的転職が盛んな業界で、応募条件に「弁理士資格(未経験歓迎)」と書いてある求人もよく見かけます。
もし特許事務所に転職するなら、スキルや意欲のほか、技術バックグラウンドの有無や一致具合も大切になります。
関連記事
【弁理士が伝授】未経験から特許事務所への転職を成功させるコツ
まとめ
弁理士は専門性が高い職種の一つです。
やめておいたほうがよい、きつい仕事だと言われることもありますが、適性のある人にはとことん合う職業です。また自身のスキルに合わせて様々な働き方を選べる仕事でもあります。
資格の取得難易度は決して低くありませんが、将来的にも必要とされると考えられるため、目指す価値は十分にあるでしょう。
今後のキャリアプランとして弁理士を検討されている人は、本記事を参考にしてみてください。
【弁理士解説!】受験生必見の弁理士試験を攻略するコツ シリーズ一覧
- 目安の勉強時間は?弁理士試験攻略のコツ
- 弁理士試験に独学で合格できる?
- 弁理士試験の難易度は?攻略のポイント
- 弁理士試験対策のおすすめ参考書9選+選び方のコツ
- 弁理士試験の短答試験に合格するためには?
- 【弁理士試験】論文式試験の有効な対策法は?勉強方法を紹介
- 【弁理士解説】弁理士試験の最終関門「口述試験」を突破するポイント
- 弁理士になるための最終関門 実務修習について
知財専門の求人サイト「知財HR」
知財業界はいわゆるニッチ業界。そこで転職時に重要になってくるのが「どれだけリアルな情報を集められるか」です。
知財HRではそんなお悩みにこたえるべく、求人票にインタビューを掲載中!(※求人によります)
一歩踏み込んだ仕事内容、職場の雰囲気、求人募集の背景など…。たくさんのリアルな情報を知ったうえで求人へ応募できるんです。求人検索は下のボタンから↓↓↓
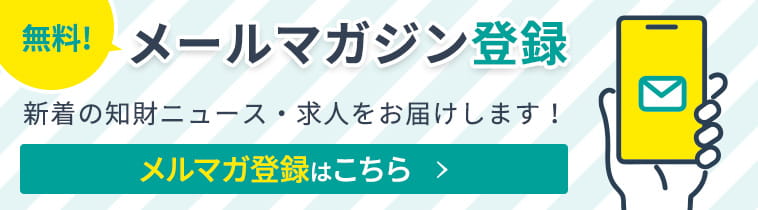


企業の研究開発部門と知財部門での業務を経験。
知財部門では、主に特許出願・権利化業務を担当してきました。

